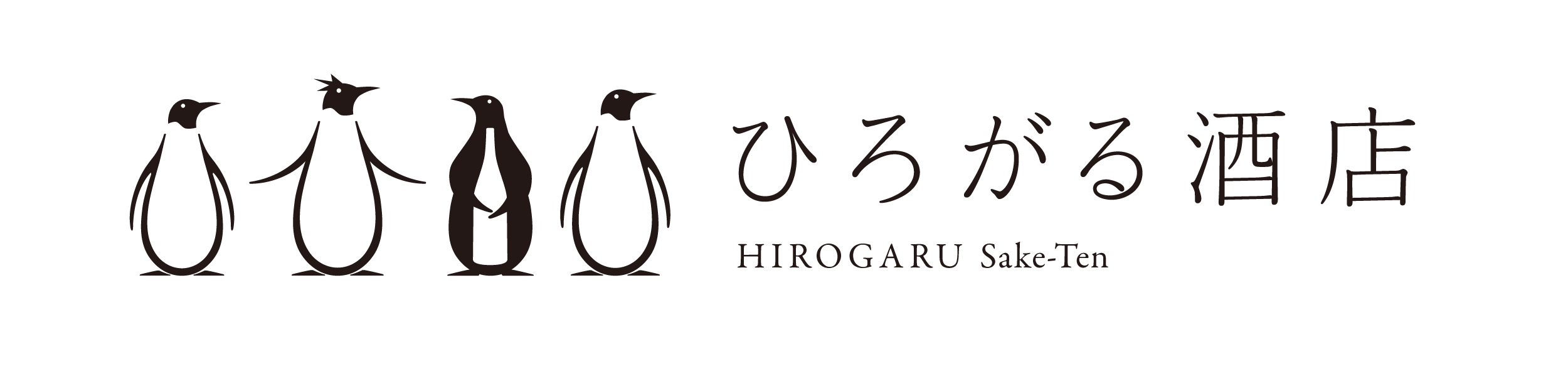Blog
2024/10/26 17:31

本日10月26日は「どぶろくの日」。どぶろくのシーズンが始まるのが10月下旬であり、「ど(10)ぶ(2)ろ(6)く」と読む語呂合わせから、濁酒(どぶろく)の魅力を広めることを目的に制定されました。
さて、皆さんは「どぶろく」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか?もしかしたら、「きつい酒」「家で作った粗雑なもの」「すぐに酔っぱらう」という印象をお持ちの方もいるかもしれません。
今回は、この偏ったイメージを払拭し、現代の(というかしっかりとした仕事によって造られている)どぶろくがどれだけ洗練されているかをお伝えしたいと思います。
◆そもそも、どぶろくって何?◆
どぶろくとは、「もろみ」を濾していない状態のお酒で、古くから日本で親しまれてきた伝統的な醸造酒のこと。
米や米麹、水を原料に、自然の力で発酵させることで生まれる、ふくよかな甘みと酸味が特徴です。
その歴史の長さから、どぶろくにはさまざまな家庭ごとのレシピがあり、それが「家庭酒」や「粗造り」といったイメージを持たれる原因の一つかもしれません。
しかし、丁寧に造られたどぶろくはその域を超え、農作物の持つ力と、そのポテンシャルを余すところなく発揮させる造り手の繊細な技術によって造られる、まさに「洗練されたお酒」なのです。
その濃厚な味わいと自然な甘みは、ただの「家飲み酒」ではなく、料理と一緒に楽しむことで新しい魅力を発見できます。
◆どぶろくは「やばい酒」なのか?◆
「どぶろくはアルコール度数が高くてすぐ酔ってしまう」という声をよく耳にしますが、実際には日本酒と同程度のアルコール度数かやや低いものが一般的です。
もちろん、どぶろく特有の発酵風味が強く感じられる場合もありますが、それが必ずしもアルコール度の強さを示すわけではないのです。
どぶろくの濃厚な口当たりは、適切な量を楽しむことで逆にゆったりとした時間を演出してくれます。特に冷やして飲むと、甘みと酸味が絶妙に調和し、スムーズに飲めるのが特徴。そして、実はお燗向きのどぶろくだってあったります。
過剰に飲まなければ、日本酒同様、悪酔いすることもありません(逆にどんなにアルコールが低いお酒だって飲み過ぎれば悪酔いしますしね)。
◆飲んだ後に体内で再発酵する…って本当?◆
「どぶろくは、飲んだら体の中でさらに発酵が進むんだ」という都市伝説のような話も時たま聞きますが、これは完全に誤りです。
発酵には、特定の温度、pH、酸素供給、糖分などが必要ですが、胃の中は強い酸性環境であり、これが酵母や他の微生物の活動を抑制し、かつ体内の代謝や消化により酵母や菌は死滅します。
ですので、どぶろくを飲んだからといって、体内でさらにアルコールが生成されたり、発酵が進行することはありません。このような誤解は、どぶろくが発酵途中の段階で飲まれるため、まだ活性のある酵母が残っていることから生まれたものと思われますが、体内では発酵が続かないことが科学的にも証明されています。
◆どぶろくを再評価しよう◆
これまでお話ししてきたように、プロの手によって造られるどぶろくは、現代の食文化にもマッチする洗練されたお酒です。
そのまろやかな甘みや豊かな風味は多様な料理と好相性で、発酵食品、スパイスの効いたカレー、はたまた素材感の強いトマトであったり、タイの昆布〆だったり、ステーキはじめ洋食に、スイーツまで。
だからこそ、どぶろくを「きつい酒」「すぐに酔っ払う」と決めつけるのはもったいない!現代のどぶろくは、造り手の想いと技によって繊細に仕上げられた、新たな食体験を提供してくれるお酒だと思います。
◆そんなこと言われても体験しないとわからない◆
ひろがる酒店では、私が言っていることを体感してもらえるであろう「でじま芳扇堂」のどぶろくを取り扱いしています。
もろみの粒感が強い「芳扇-友-」、切れ味重視の辛口タイプ「芳扇-波-」、とろとろな口当たりの甘口タイプ「芳扇-雲-」、そして米以外の農作物にスポットをあてる異色のどぶろく「たすきシリーズ」。
長く書きましたが、やっぱり論より証拠だと思います。
新しいどぶろく体験にご興味ある方は是非!
さて、皆さんは「どぶろく」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか?もしかしたら、「きつい酒」「家で作った粗雑なもの」「すぐに酔っぱらう」という印象をお持ちの方もいるかもしれません。
しかし、それはどぶろくに対する誤解です。
◆そもそも、どぶろくって何?◆
どぶろくとは、「もろみ」を濾していない状態のお酒で、古くから日本で親しまれてきた伝統的な醸造酒のこと。
米や米麹、水を原料に、自然の力で発酵させることで生まれる、ふくよかな甘みと酸味が特徴です。
その歴史の長さから、どぶろくにはさまざまな家庭ごとのレシピがあり、それが「家庭酒」や「粗造り」といったイメージを持たれる原因の一つかもしれません。
しかし、丁寧に造られたどぶろくはその域を超え、農作物の持つ力と、そのポテンシャルを余すところなく発揮させる造り手の繊細な技術によって造られる、まさに「洗練されたお酒」なのです。
その濃厚な味わいと自然な甘みは、ただの「家飲み酒」ではなく、料理と一緒に楽しむことで新しい魅力を発見できます。
◆どぶろくは「やばい酒」なのか?◆
「どぶろくはアルコール度数が高くてすぐ酔ってしまう」という声をよく耳にしますが、実際には日本酒と同程度のアルコール度数かやや低いものが一般的です。
もちろん、どぶろく特有の発酵風味が強く感じられる場合もありますが、それが必ずしもアルコール度の強さを示すわけではないのです。
どぶろくの濃厚な口当たりは、適切な量を楽しむことで逆にゆったりとした時間を演出してくれます。特に冷やして飲むと、甘みと酸味が絶妙に調和し、スムーズに飲めるのが特徴。そして、実はお燗向きのどぶろくだってあったります。
過剰に飲まなければ、日本酒同様、悪酔いすることもありません(逆にどんなにアルコールが低いお酒だって飲み過ぎれば悪酔いしますしね)。
◆飲んだ後に体内で再発酵する…って本当?◆
「どぶろくは、飲んだら体の中でさらに発酵が進むんだ」という都市伝説のような話も時たま聞きますが、これは完全に誤りです。
発酵には、特定の温度、pH、酸素供給、糖分などが必要ですが、胃の中は強い酸性環境であり、これが酵母や他の微生物の活動を抑制し、かつ体内の代謝や消化により酵母や菌は死滅します。
ですので、どぶろくを飲んだからといって、体内でさらにアルコールが生成されたり、発酵が進行することはありません。このような誤解は、どぶろくが発酵途中の段階で飲まれるため、まだ活性のある酵母が残っていることから生まれたものと思われますが、体内では発酵が続かないことが科学的にも証明されています。
◆どぶろくを再評価しよう◆
これまでお話ししてきたように、プロの手によって造られるどぶろくは、現代の食文化にもマッチする洗練されたお酒です。
そのまろやかな甘みや豊かな風味は多様な料理と好相性で、発酵食品、スパイスの効いたカレー、はたまた素材感の強いトマトであったり、タイの昆布〆だったり、ステーキはじめ洋食に、スイーツまで。
だからこそ、どぶろくを「きつい酒」「すぐに酔っ払う」と決めつけるのはもったいない!現代のどぶろくは、造り手の想いと技によって繊細に仕上げられた、新たな食体験を提供してくれるお酒だと思います。
◆そんなこと言われても体験しないとわからない◆
ひろがる酒店では、私が言っていることを体感してもらえるであろう「でじま芳扇堂」のどぶろくを取り扱いしています。
もろみの粒感が強い「芳扇-友-」、切れ味重視の辛口タイプ「芳扇-波-」、とろとろな口当たりの甘口タイプ「芳扇-雲-」、そして米以外の農作物にスポットをあてる異色のどぶろく「たすきシリーズ」。
長く書きましたが、やっぱり論より証拠だと思います。
新しいどぶろく体験にご興味ある方は是非!